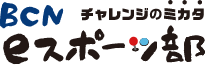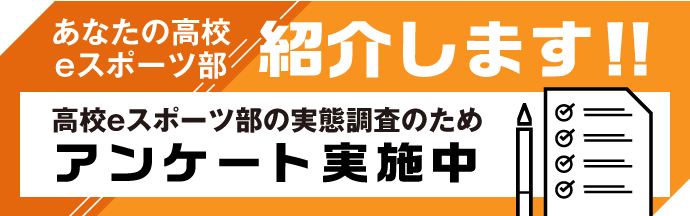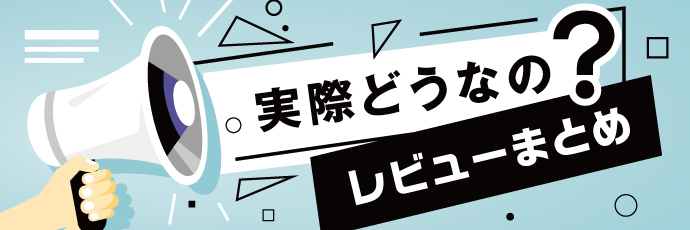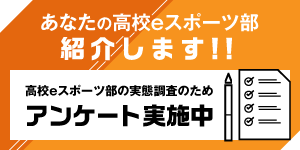インタビュー
2025.04.11
群馬の“ゲーミングおかん”に聞く「親子とゲームの付き合い方」、チーム運営に親参加
- インタビュー
ついつい時間を忘れて夢中になってしまうeスポーツとの付き合い方は、家庭によってさまざまです。いさかいの種になってしまうこともありますが、時には親子のコミュニケーションを生むきかっけにもなります。今回は、「ゲーミングおかん」の愛称で親しまれる、群馬県eスポーツ連合の事務局長 倉林亜希子さんに、家庭におけるゲームとの付き合い方や、eスポーツに打ち込む子どもに対する保護者としての関わり方について話を伺いました。
(取材・文/松永華佳 編集/小川翔太)

倉林亜希子さん
家庭内のトラブルが発覚 ──息子が内緒で我が家のルールを破っていた
──倉林さんがeスポーツに関わるようになったきっかけを教えてください。
倉林さん(以下、敬称略) もともとは広告代理店で雑誌や書籍の編集、イベント企画などを担当していました。2019年春から会社でeスポーツを担当することになり、それが私のeスポーツとの出会いです。
私自身はゲームにあまり詳しくなく、むしろデジタルが苦手な方でした。実は、ビデオ予約も取れないぐらいデジタル音痴です(笑)。
そんな状態からスタートしましたが、2020年からは群馬県eスポーツ連合(gespo/ゲスポ)の業務執行理事兼事務局長に就任。現在はeスポーツ事業を手掛ける、LANNERの代表取締役も務めています。

(eスポーツ×ビジネスカンファレンス GUNMA2025)
──倉林さんは「ゲーミングおかん」の愛称で親しまれていますが、ご自身のお子さんがゲームやeスポーツをすることについてはどうお考えですか。
倉林 子どもたちがゲームをすること自体は、時代の自然な流れだと思いますが、家庭でのルール作りは大切だと考えています。我が家では「平日は1時間、週末は2時間」「ゲームは自室ではなくリビングで」などのルールを設けています。
これは学校の宿題やお稽古事とのバランスなどを考えると、我が家では必要なルールだと思っています。ところが最近、息子が数カ月にわたってこっそりルールを破っていたことがわかりました。
ゲーム購入の際に息子の意見も聞いて、家族で話し合って決めた大切なルール。それを破ったこと、何カ月も隠していたこと、そして全く気づけなかった自分自身と、いつバレるのかと不安だった息子の気持ちを思うと色々な感情があふれてしまって……。
お恥ずかしながら、eスポーツの仕事をしている私でさえ、我が子のこととなると冷静になれず、感情的に叱ってしまいました。その後、落ち着いて話し合い、アプリを全てアンインストールさせ、この一件は収まりました。
息子からは「自分が初めて作ったゲームのアカウントだけは残したい」と言われましたが、信用を失う行為をした以上、例外は認めませんでした。

(大きい声では言えない)ゲーミングおかんはゲーム依存症!?
──この手の家庭内トラブルは、昨今のニュースでも良く取り扱われていますね。
倉林 そうですね。このトラブルから学んだのは、スマホを持たせる際のルール作りの大切さです。
息子に対して何年間も改めてのルール確認をしなかったことを、当時は反省しました。その後、下の娘がスマホを持った時には、息子も一緒にルール作りに参加してくれました。自分の経験を活かして妹にアドバイスもしてくれたんです。
私自身も「ゲーミングおかん」として活動する中で「親の立場」と「仕事の立場」、両方の視点からゲームと向き合うことの重要性を実感しています。子どもたちには適切な距離感でゲームを楽しんでほしいですし、そのためには親も一緒に理解を深める努力が必要です。
──ちなみに、倉林さん自身はゲームをプレーされますか。
倉林 大きな声では言えませんが、実はいま私は「ゲーム依存症」なのかもしれません(笑)。
スマホのパズルゲームにハマっていて、昨日も寝る時間を惜しんでプレーしていたので、少し寝不足気味です。
自分でも「矛盾している」という自覚があります。
子どもたちにゲームの時間を制限している親の立場でありながら、私自身は夜更かしをしてまでゲームをやることもあります。
家庭用ゲーム機のゲームにハマっていた時は、子どものために設定したペアレンタルコントロール機能で確認した夫に、「また夜中ゲームやってただろ」と指摘されることもあります。もしルールを課せられていたら、私が一番破っていたのかもしれません。
ただ、このような経験も、子どもたちとゲームについて話す時の共通言語になっていると感じています。自分自身がゲームの楽しさとコントロールの難しさを知っているからこそ、適切な距離感やルール作りの大切さも実感できるのだと思います。

群馬県eスポーツ連合gespoの取り組み──「ゲーミングおかん」チームを結成したい
──現在gespoで取り組まれていることについてもお聞かせください。
倉林 私自身、当初はゲームに対して後ろ向きな印象を持っていました。だからこそほかの保護者の方々の気持ちがよく分かるんです。そこで今、個人的にチャレンジしたいのが、保護者の方々がeスポーツの運営に参加できる環境づくりです。
具体的には、「eスポーツ運営チーム」に保護者、特にゲームに反対しがちなお母さんたちに入ってもらう取り組みを計画しています。野球などの部活動で保護者が送迎したり現場で世話を焼いたりするように、eスポーツでも親世代が運営スタッフとして関わる仕組みを作りたいと考えています。
ボランティアやアルバイトとして学生さんが来てくれることも多いのですが、理想的なのは親世代や祖父母世代も一緒に来てくださることです。ゲームに詳しくなくても、子どもたちへの接し方やコミュニケーションの取り方を知っている方々は、運営面で大きな力になります。
皆さんにも「ゲーミングおかん」として運営に参加していただくことで、保護者自身のゲームへの理解が進み、同時に子どもたちが楽しむ場を作るサポートができると考えています。
何よりも「子どもが楽しんでいるものを自分も理解したい」という思いがあれば、ゲームの知識は後からついてくるので、心配はありません。
──将来ご自身のお子さんが、今の倉林さんが行っているように「eスポーツを広める仕事がしたい」と言った場合はどのような反応をされますか。
倉林 もし子どもがeスポーツの仕事をしたいと言ってきたら、全力で応援したいと思います。eスポーツでもほかのどんな仕事でも、子どもがやりたいと思うものであれば応援する気持ちでいます。
私自身が今やっている仕事には誇りを持っていて、とても面白い半面、難しさも感じています。だから「面白い仕事だけど、やれるものならやってみなさい」と言うでしょうね。
それでも子どもたちが「やる」と言ったら、これまで培ってきたノウハウも出したいですし、全面的にサポートするつもりです。
親次第で子どもの可能性も広がるでしょうし、選択肢を狭めないようにしたいと考えています。

ゲームを通じて、久しぶりに息子に「ありがとう」と伝えられた──親世代は「分からない」からといって“理解”を諦めてはならない
──親子関係において、ゲームを通じた印象的なエピソードはありますか。
倉林 ゲームを通じて、久しぶりに息子に「ありがとう」と伝えられたことに気づいた瞬間がありました。
息子が中学生で、思春期真っ只中だった頃のことです。普段は「勉強しなさい」「いつまでゲームしてるの」と否定的なことばかり言っていました。
ある時、私の仕事の関係でeスポーツのチームを組む機会があり、息子に手伝ってもらうことになったんです。その際、息子が私をキャリー(サポート)してくれて、「ママ、この武器使っていいよ」とか「包帯も使って」と持ってるアイテムを次々に教えてくれたんです。私がゲーム内でやられちゃって「ごめん!」と言った時も、息子が「いいよいいよ、大丈夫」と助けてくれました。
咄嗟に「ありがとう」と息子に伝えた時に、「あれ、そういえばもう数ヶ月も息子にありがとうって言ってなかったな」と気づいたんです。小さい頃はなんでもないことでもよく褒めていたのに、中学生にもなったら、あまり褒め言葉を伝えることもなくなってしまいました。
思春期で普段は会話も少なくなっていた息子と、ゲームをきっかけにコミュニケーションが生まれたのは貴重な経験でした。もちろん良い関係でずっといられたわけではないですが、思春期という難しい時期を乗り越えるのに、ゲームには助けられたと実感しています。

──これを読んでいる親御さんたちに向けて、保護者の立場としてeスポーツやゲームとどう向き合えば良いのかアドバイスをお願いします。
倉林 子どものゲームを「フィジカルスポーツなどと同じように捉える」と分かりやすいと思います。例えば、サッカーや野球などのスポーツなら、保護者は(自主的に)ルールを覚えたり試合を見に行ったりするのに、ゲームになると「ルールが分からない」と一歩引いてしまう方が多いです。
具体的には、あるご両親が「息子がプロになりたいと言っている」と親子でgespoに相談に来られたことがありました。詳しく話を聞くと、その子は本格的な練習をしておらず、大会への出場経験もなく、世界レベルで戦える状態にはほど遠い状況でした。
しかし、もしこれがサッカーや野球だったら、親はルールを覚えたり、子どもの試合を見に行ったり、どんな練習が必要かを調べたりするはずです。でも、ゲームになると急に「分からない」という壁ができてしまう。私自身も「デジタル音痴」なので、その気持ちはよくわかります。
でも、自分が得意でなくても、「このゲームは何人制なのか」「どうやって見たらいいのか」といった基本的なことを知ろうとする姿勢は必要です。分からなければ子どもに聞いてみるのもいいですし、そうした会話自体がコミュニケーションになります。そうすれば方針や進路など、今後の話もできるはずです。

──倉林さんありがとうございました!
関連記事
芸人・プロゲーマー・アナリストを歴任したJapanese小池さんに聞く学生時代とキャリア、「困難を乗り越えた経験が今につながる」
大切なことは“ゲーセン”が教えてくれた── 日本初のeスポーツドクターREKKAさんに聞く学生時代とキャリア
【前編】「自分のやってきたことを記録に残す 改めて大事と実感」日本人初のスマブラコーチ Crazy Raccoon カイトさんに聞く キャリアと仕事
外部リンク
群馬県eスポーツ連合
Gunma esports Union(gespo/ゲスポ)
https://gunma-esu.com/

おすすめ関連記事
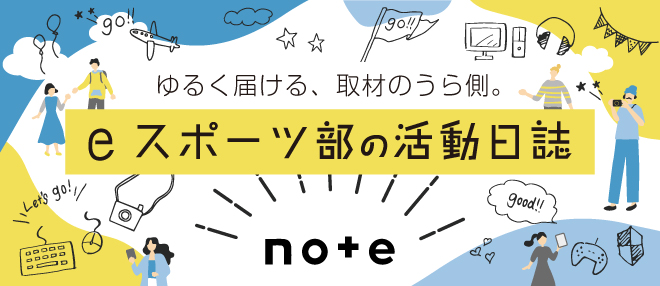

高校eスポーツ探訪
-

2025.03.29
300年の歴史を誇る伝統校でeスポーツが部活動に 広島県 修道中学校・修道高等学校 物理班 eスポーツ部門 活動内容を聞いてみた!
-

2024.08.02
eスポーツが学校生活の活力に 立正大淞南eスポーツ部「GEEK JAM」 ランクイモータルのプロ志望も入部!? 部員インタビュー

記事ランキング
-
1

施設
2025.06.11
愛知・一宮に隠れ家的eスポーツ施設が誕生 オープニングイベントに元SKE48犬塚あさなさんらゲスト登場 施設の無料開放も
-
2

解説
2021.10.19
ネトゲでよく使われる用語(スラング)一覧|意味や使い方を紹介!
-
3

サービス
2025.06.03
伊予鉄も協力で駅周辺を再現 フォートナイト活用した愛媛・松山舞台のゾンビゲームが登場 松山中央商店街「土曜夜市」でのリアルイベントも予定
-
4
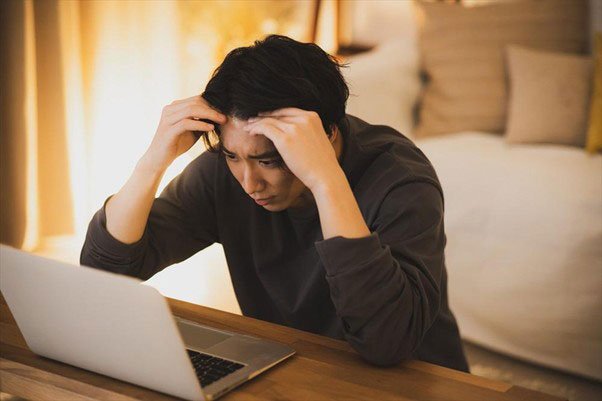
解説
2025.05.05
再起動の前に確認しよう!PCがフリーズしたときの原因と対処法をわかりやすく解説
-
5
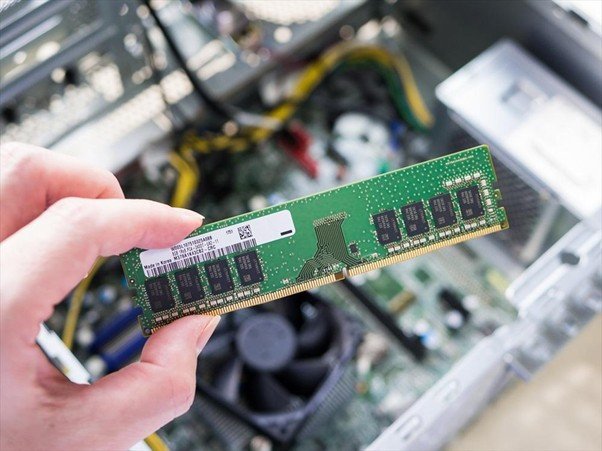
解説
2025.05.07
PCの動作が重いのは「RAM」が原因かも?RAMって何?ROMやストレージとの違いもあわせて解説